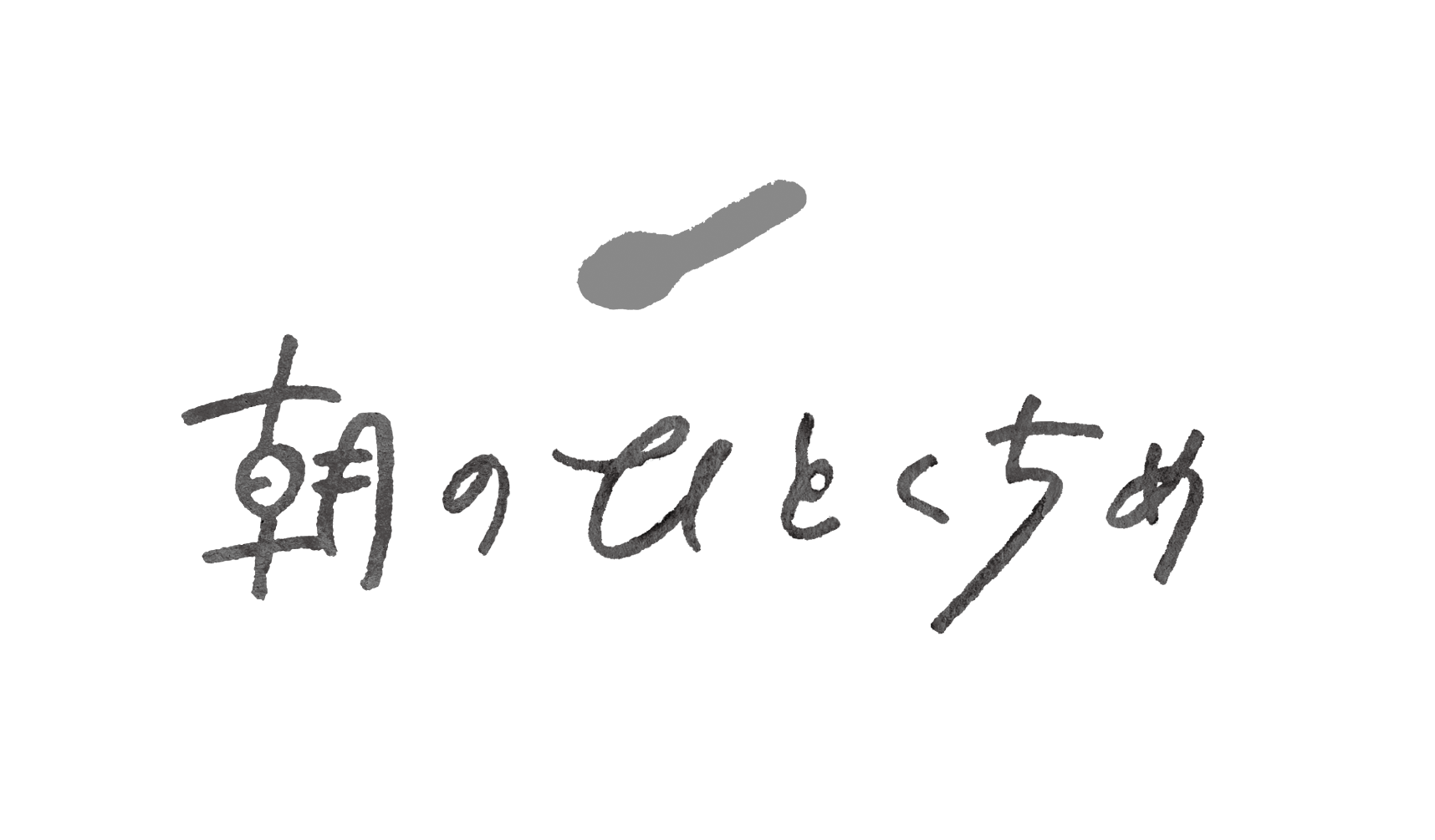2024/10/13 13:47
2024年度日本調理科学会中国・四国支部 研究発表会にて、朝のひとくちめが広島大学と共同で開発した離乳食「お守りお野菜ペースト」に関する口頭発表を行いました。
2022年から2年に渡り共同で開発を行ってきたなかで、当時3年生だった学生さんがお守りお野菜ペーストの開発工程と並走しながら「志和町産野菜の特徴」と「離乳食として嗜好生の良好な加熱時間」に関する研究を行うことを決定し、4年生の卒業研究として様々な調査・分析を行ってくれました。その研究結果を、共同研究者として朝のひとくちめ 田野実が学会にて発表いたしました。


野菜の探究をしていたはずが、それは人間の探究でした
この研究では「官能調査」「機器分析」の両面から分析しており、機器分析のみの結果も多い論文において、この両方を行った内容であることがとてもうれしく感じます。「数値では確かにそうなっているけど、実際おいしいの?」と思うことがとても多くあったからです。今回の研究でも、機器分析では確かに有意差があるものの官能評価では差がない、という結果が多くありました。実際、人がどう感じているのか?ということを数値と比較しながら見ていくと、結局は野菜の探究をしていたのに人間の探究に行き着きます。物質的には同じものを食べているのに感じ方が違ってくるその多様さを見ていると、好みの背景にはそれまでの人生経験も含めた様々な要素が絡み合っているのだなと感じます。千差万別すぎる人類に対して食べ物を生み出していくという、深掘りするほどわからなくなっていきそうな世界に、おもしろさとやりがいをさらに強める体験となりました。
食べる人にとって、”いま”必要な目的を考える、という視点
発表に対し熱心なご質問もいただき、食べ物を作る上で「目的」によって研究ポイントも最終的なレシピも変わってゆくことを感じました。「おいしい体験をすること」「健康維持のために栄養素を効率的に摂取すること」「体調・場面にあった形やテクスチャーであること」この「見た目・味・香り」「栄養」「物性」3つのバランスを常にとりながら、レシピを設計していく必要性を感じました。
これまでは「おいしさ・美しさ」を追求することを重要視してきたということを再認識すると同時に、離乳食という特殊時期の食べ物の開発に取り組んだことから、食べ物を生み出す際の「目的」の設定がとても重要であることに気付かされました。

図に表したように、人が仮に100年生きられるとしたら、離乳食期はほんの一瞬です。また、人生が終わりに近づくときどの程度特殊な食べ物が必要になってくるかというのは、きっとそれまでその人が毎日繰り返してきた「習慣」によって、始まりも、長さも変わってくるのだと思います。
食べてほしい相手がいたとき、その人の置かれた体調と環境があり、その人の好みや背景にある人生のフェーズに合わせて、生み出す食べ物を設計していくことが必要なのですね。さらには、「時間栄養学」という学問もあるように、食べる時間帯によっても吸収率や必要性が変わってくることから、「時間=シーン」という視点も外せません。

Icons by Icons8
朝のひとくちめとしては、やはり「おいしい・楽しい」という部分に重きを置きつつも、その次に来る目的をどこにおくかを様々な要素から順位づけし設定しながら食べ物を生み出していきたいと感じました。
今回の論文は、まだ学会での発表段階のため論文化はされていません。また公開できる日が来ましたら、ご紹介できたらと考えています。まだまだ探究の入り口、これからも朝のひとくちめの野菜と人間へのおもしろさ探究の結果を発信していきますので、一緒におもしろがってくれましたら幸いです。
研究を頑張ってくれたMちゃん、企画段階から発表までの多大なる支援をいただいた広島大学 冨永先生、神戸大学 湯浅先生、佐賀大学 萱島先生このような機会をいただきありがとうございました。
CONFERENCE:2024年度調理科学会中国・四国支部 研究発表会
PLACE:香川短期大学
DAY:2024/10/12
最後に、香川県ならではのうどんに関するランチセミナーの様子を写真でご紹介します。うどんをお皿に盛り付ける際の手捌きから、うどんを取り扱い慣れていらっしゃることがよく感じられました。